科目学習書●[メディアテクノロジー論]/[マルチメディア活用論]
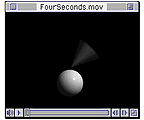
いろいろな感覚を通じて伝える
●
ムービ
時間の配置
△
http://www.infonet.co.jp/apt/March/syllabus/MedTech/movie.html
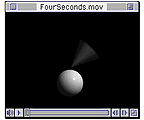
ふつうの意味でのムービ(movie=映画)にTVやVHSビデオ、DVDビデオなどを含めたものをムービという。
この単元では、ムービの構造について学習する。続いて、記録/通信に用いられている媒体、フォーマット、コーデックについて学習する。
この単元では、ムービの構造について学習する。続いて、記録/通信に用いられている媒体、フォーマット、コーデックについて学習する。
もしまだならここで
|
ビデオの構造 |
オーディオの構造 |
ムービの構造
映画やTV、ビデオソフトは、流通の制度や媒体の形式はいろいろ違っているけれど、ビデオとオーディオとの組合せとして構成されているという点ではよく似ている。これらをまとめてムービ(movie、または動画像。資料[ムービ])という。
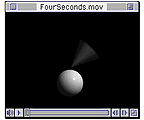
ムービに含まれているビデオとオーディオは、それぞれムービの最初から最後までにわたって時間に沿って続いている互いに平行な線のようなものと見なすことができる。これらをトラック(track。▽図。資料[トラック])という。
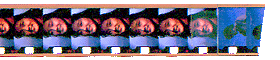
△
ムービが記録されているシングル-8フィルム
ビデオトラック(中央の一連のフレームの列)と2本のオーディオトラック(両端の茶色に見える線)とが並行して記録されているのが分る
ビデオトラックやオーディオトラックをそれぞれ複数本ずつ含んでいるムービもある。これらのトラックは、視界を広くしたり(→資料[シネラマ])、音が聞こえてくる方向を再現したり(→資料[5.1チャネル])、せりふを言語によって切り替えたりするのに使われている。

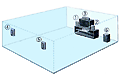
これらのほかに、せりふの意味などを字幕として表示するためのテキストのトラックや、(DVDのタイトルやウェブのページなどの)ほかのコンテンツを呼び出すためのリンクのトラックがムービに追加されることもある。
オプション
ムービの制作
Premiereという、広く使われているムービ編集システムがある。先生が、ムービ制作システムの[Premiere](▽図)を使ってムービの編集、向きや大きさや色などの調整をして見せるのでその感じを確かめなさい。
Premiereの表示を見ていると、トラックやフレームの感じもつかみやすいだろう。
Premiereの表示を見ていると、トラックやフレームの感じもつかみやすいだろう。

△
Premiere
ムービは、絵や音などのいくつもの素材を組合せて作られている。このそれぞれの素材をクリップ(clip)という。ムービ制作システムを使うと、ムービを作る作業は、クリップを時間に沿って並べたり、重ね合せたり、上下左右に並べたりすることに還元される。この作業を行なう台紙にはタイムライン(timeline)とステージ(stage)とがある。タイムラインは時間に沿った並び方と重ね合せを決めるのに使い、ステージは上下左右の並び方を決めるのに使う。クリップとその並べ方や重ね方とを組合せたものを出番という。
タイムラインやステージに並べる素材を置いておく容器をキャスティングボックス(casting box)という。
先生が、[Premiere](▽図)を使って、絵や音に特別な効果をかけて見せるのでその感じを確かめなさい。
ムービ制作システムを使えば、クリップの並べ方や重ね方を決めたり直したりするほかに、絵や音の調子を変えることもできる。ただ、このような作業は、絵や音をそれぞれ専門に取り扱うシステムを使って、編集の前(またはあと)に行なうことも多い。
タイムラインやステージに並べる素材を置いておく容器をキャスティングボックス(casting box)という。
先生が、[Premiere](▽図)を使って、絵や音に特別な効果をかけて見せるのでその感じを確かめなさい。
ムービ制作システムを使えば、クリップの並べ方や重ね方を決めたり直したりするほかに、絵や音の調子を変えることもできる。ただ、このような作業は、絵や音をそれぞれ専門に取り扱うシステムを使って、編集の前(またはあと)に行なうことも多い。
オプション
レンダリング
タイムライン/ステージに組み立てられたムービをそのまま再生しようとすると、いくつものクリップの配置や効果を同時に考え合わせながら、再生するのに間に合うように絵や音を作り続けていかなければならないので、望ましい品質はとても得られない。そこで、実際に見せる目的のムービは、タイムライン/ステージの形式とは別に、配置や効果を入れ込んでしまったあとの、もっと単純な形式に直してから記録/送信される。こうすれば、単純な形式を作る作業は前もってやっておけるので、ゆっくり時間をかけて行なうことが可能になる。この作業をレンダリング(rendering。またはmixdown)という。
ムービの表現
ムービを記録/通信するための形式にはいろいろなものがある。ムービの形式は、媒体、フォーマット、コーデックの三つの階層に分けて考える必要がある。
ムービの通信に使われる媒体
ムービの通信には、一般の通信と同じように電波(electromagnetic wave、電磁波)、金属線、光ケーブルなどが使われている。
日本では、電波を使ったTV放送では、超短波(Very High Frequency)、極超短波(Ultra High Frequency)、センチ波(Super High Frequency)を使っている(▽図。資料[電磁波])。
日本では、電波を使ったTV放送では、超短波(Very High Frequency)、極超短波(Ultra High Frequency)、センチ波(Super High Frequency)を使っている(▽図。資料[電磁波])。
| 地上アナログ放送 |
超短波 極超短波 |
| 地上デジタル放送 | 極超短波 |
| 衛星放送 | センチ波 |
ムービの記録に使われる媒体
ムービの記録には▽図のような媒体が使われてきた。
|
フィルム 8mm 16mm 35mm 70mm |
|
ビデオテープ Uマチック ベータマックス VHS Hi-8 DV |
|
レーザディスク VHD レーザディスク |
|
ビデオCD CD-ROM CD-R CD-RW |
|
DVDビデオ DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM Blu-ray |
ムービの記録に使われる媒体
ムービフィルム
劇場用映画のほとんどは、撮影や編集から上映までのほとんど全部の工程を、ムービフィルムを使って行なっている。ムービフィルムでは、全部の方向に(実質的には)連続なフレームを単位として、写真と同じフィルムにムービを記録する。
ムービフィルムは、品質がいいことや記録の状態が目で直接に確かめられることから、一時はTVでも一部の番組の制作や記録に使われたり、家庭用のムービの記録の手段として使われたりしたが、そのどちらでもほとんどVTRがとって代わっている。また、劇場用映画でも、編集や上映の一部ではフィルムを使わない方式が取り入れられるようになってきている。
Single-8フィルムの実物を分解してしくみを確かめよう。
ムービフィルムは、品質がいいことや記録の状態が目で直接に確かめられることから、一時はTVでも一部の番組の制作や記録に使われたり、家庭用のムービの記録の手段として使われたりしたが、そのどちらでもほとんどVTRがとって代わっている。また、劇場用映画でも、編集や上映の一部ではフィルムを使わない方式が取り入れられるようになってきている。
Single-8フィルムの実物を分解してしくみを確かめよう。
ムービの記録に使われる媒体
VTR
現在では、ムービを作ったり見たりするための最も手軽なメディアとしては、VTR(video tape recorder)が使われている。
多くのVTRでは、コンピュータでビデオを扱う場合と同じように、ビデオをフレームに、さらにラスタに分解して記録する手法が使われていた(→資料[VTR])。
(DV以前の方式の)VTRでは、コンピュータの場合とは違って、ラスタはセルに分割されていない。このためVTRでは、ラスタの方向については、色の連続的な変化をそのまま正確に記録することができる。また、ラスタは微妙に右下がりに傾いていて、右端と次のラスタの左端との高さが揃うようになっている(▽図)。
多くのVTRでは、コンピュータでビデオを扱う場合と同じように、ビデオをフレームに、さらにラスタに分解して記録する手法が使われていた(→資料[VTR])。
(DV以前の方式の)VTRでは、コンピュータの場合とは違って、ラスタはセルに分割されていない。このためVTRでは、ラスタの方向については、色の連続的な変化をそのまま正確に記録することができる。また、ラスタは微妙に右下がりに傾いていて、右端と次のラスタの左端との高さが揃うようになっている(▽図)。


△
VTRのラスタ(DV以前)
もとのフレーム(左)と記録されたもの(強調してある)
TVやVTRでは(方式によってはコンピュータでも)、フレームを構成するラスタは、単純に上下の順に記録されているわけではない。VHSなどでは、初めに偶数番目(0、2、...番目)のラスタだけを順に記録し、そのあとで残りの奇数番目(1、3、...番目)のラスタを順に記録する。この方式をインタレース方式(interlacing-)といい、偶奇に分けない方式を非インタレース方式という。インタレース方式を使うと、再生してちらつきが見えるのを押さえることができる((→資料[インタレーシング]、課題[ちらつき])。


△
インタレーシングのない表示(左)とインタレーシングのある表示(右)
VTRでは、色の違いを表現するのには、RGBモデルではなく、明るさ、赤み、緑みの三つの属性の組合せで表現するYCCモデルが使われている(>課題[YCC])。つまり、VTRの画像は明るさ、赤み、緑みの三つの属性の変化を表す3本のグラフの組みとして表現されることになるが、この3本は、磁気の強弱に置き換えられて、1本のテープの上にうまく重ね合さって記録されている(>課題[多重化])。
VTRには、少しずつ違ういくつかの方式がある。家庭用としてはVHSやHi-8、放送用としてはベータカムなどの方式がよく使われてきたが、最近では新しい方式としてDVが登場し、これらに代わろうとしている。
VTRテープの実物を分解してしくみを確かめよう。
VTRには、少しずつ違ういくつかの方式がある。家庭用としてはVHSやHi-8、放送用としてはベータカムなどの方式がよく使われてきたが、最近では新しい方式としてDVが登場し、これらに代わろうとしている。
VTRテープの実物を分解してしくみを確かめよう。
ムービの記録に使われる媒体
DVD
ムービのフォーマット
ムービを記録/通信するためのフォーマットとしては▽図のようなものが使われてきた。
|
コンピュータ インタネット |
QuickTime rm AVI WM9 |
|
TV(アナログ) テープ形態ビデオソフト |
ベータマックス VHS Hi-8 DV |
|
TV(デジタル) ディスク形態ビデオソフト ポータブルプレーヤ |
MPEG-1 VOB MPEG-2 MPEG-4 |
|
映画 |
(各フィルムに対応したフォーマット) |
|
電話 |
H.264 |
|
DV MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 H.264 |
これらのほかに、特定のフォーマットでしか使われない専用のコーデックがある。
フォーマットの中には、単一のコーデックだけに対応しているものもあるし(たとえばコーデックとフォーマットが同じ名前のもの)、複数のコーデックに対応しているものもある(QuickTime、WM9など)。
MPEG-2などでは、いろいろな度数(左右/上下のセル数、フレーム数/秒、インタレース数など)については範囲だけが決められている。しかし、特定の度数の組み合せを決めておいてそれを共通に使うようにしておくと便利なので、標準の組み合せがいくつか決められている。これらをレベルという。TVの放送では(したがってビデオテープの録画でも)、これに当たる規約として、NTSC、PAL、SECAMの3種類が決められている。
フォーマットの中には、単一のコーデックだけに対応しているものもあるし(たとえばコーデックとフォーマットが同じ名前のもの)、複数のコーデックに対応しているものもある(QuickTime、WM9など)。
MPEG-2などでは、いろいろな度数(左右/上下のセル数、フレーム数/秒、インタレース数など)については範囲だけが決められている。しかし、特定の度数の組み合せを決めておいてそれを共通に使うようにしておくと便利なので、標準の組み合せがいくつか決められている。これらをレベルという。TVの放送では(したがってビデオテープの録画でも)、これに当たる規約として、NTSC、PAL、SECAMの3種類が決められている。
ムービのフォーマット
MPEG
ムービ(や単独のビデオ/オーディオ)を記録したり保存したりするため広く使われている標準のフォーマットの一つにMPEG1/2/4がある。MPEGの使われ方としくみ(特にビデオの部分)について学習し、それを通じてメディアとしてのビデオの特徴を理解しよう(→資料[MPEG])。
MPEGでは、いろんな手法を盛り込んで、少しでも容量のむだを節約しようとしている。MPEGの核心は、書式化/官能化の手間は増やして、それと引き換えに媒体の負荷を減らす、という考え方にある。特におもしろいのはずれ圧縮の考え方だ。
先生から、実際の映画の連続したフレームを印刷したものをもらい、6×4ぐらいに分割して、自分で実際に(大まかでかまわないから)ずれ圧縮をしてみなさい。
MPEGでは、いろんな手法を盛り込んで、少しでも容量のむだを節約しようとしている。MPEGの核心は、書式化/官能化の手間は増やして、それと引き換えに媒体の負荷を減らす、という考え方にある。特におもしろいのはずれ圧縮の考え方だ。
先生から、実際の映画の連続したフレームを印刷したものをもらい、6×4ぐらいに分割して、自分で実際に(大まかでかまわないから)ずれ圧縮をしてみなさい。
> もっと深く学習するための問題 <
ジャンクション
▽
映像
△
このページの記事の一部は 著作者への配慮や媒体の容量の都合によって バージョンによっては見ていただくことができない場合があります
Copyleft(C) 2003-07, by Studio-ID(ISIHARA WATARU). All rights reserved.
最新更新
07-07-08