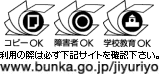|
|
トランジスタ (transistor) |

形状・サイズには様々なものがありますが、 左の写真はその一例です。 コンピュータには膨大な数の (おそらく 100 億個ほどの…) トランジスタが使われていますが、 ほとんどは IC の中に集積されていて、 このような単体のトランジスタが使用されることは希です。
トランジスタにはエミッタ (emitter)、 ベース (base)、 コレクタ (collector) という 3 つの電極があります。
NPN 型トランジスタの場合、 ベースからエミッタにほんの少し (たとえば 1mA 程度の) 電流を流してやると、 その数百倍の電流がコレクタからエミッタに流れます。 ベースの電流を変化させるとコレクタの電流もそれに応じて大きく変化し、 ベースの電流を止めるとコレクタ‐エミッタ間にも電流が流れなくなります。
トランジスタにはベースの電流の変化を拡大する 「増幅作用」 と、 コレクタ電流をベース電流で ON-OFF する 「スイッチング作用」 があり、 コンピュータではもっぱらこのスイッチング作用が利用されています。
PNP 型トランジスタは電流の流れる方向が NPN 型トランジスタとすべて逆になります。 下図の左は NPN 型トランジスタ、 右が PNP 型トランジスタです。
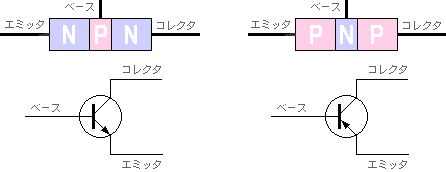
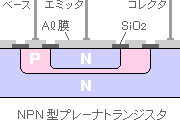
当時はそんなに薄いベース層を挟んだ NPN、 あるいは PNP 接合を実際に作ることはできませんでした。
その後合金型、 成長型、 メサ型など、 様々なトランジスタが試されましたが、 現在は左図のような構造のプレーナ型トランジスタを量産する技術が確立されています。
また今日、 これがさらに IC に発展し、 半導体製造技術の礎となっています。
トランジスタは 20 世紀の最大の発明のひとつであり、 文字通り 「小さな巨人」 でもあります。