|
|
昆虫の情報媒体・フェロモン(情報伝達) |
植物の情報伝達については、まだ解明されているところが少ないが、
昆虫については、広く情報媒体として用いられて、
フェロモンと呼ばれている気体について、すでに多くのことが明らかになっている。
特に、メスがオスを誘引するために分泌発散させる性フェロモンは、
ホタルのように光を用いたり、コオロギのように音を用いたりする場合を除いて、
大部分の昆虫で用いられており、現在約500種を超えるものが知られている。
昆虫の性フェロモンについての研究は1950年代から行われたが、
最初にその物質が明確に同定されたのはカイコの性フェロモン「ボンビコール」で、1961年に、
それが「トランス-10、シス-12、ヘキサデカンジエン−1−オール」という構造であることが明らかになった。
その後、機器分析法の発展にも助けられて、
次々と多くの昆虫について性フェロモン物質の構造が解明されていった。
そして、今日では、それらは 「地球にやさしい」 無公害な害虫駆除剤として、
実際の農業においても利用されている。
すなわち、合成された性フェロモンによってオスを大量に誘引して捕殺する 「大量誘殺法」 や、
合成された性フェロモンを高濃度に散布して、メスがどこに居るのかをオスに分からなくさせて、
その繁殖を阻害する 「交信攪乱法 」である。
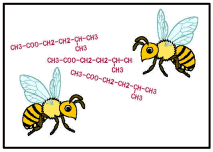
![]() フェロモンには、性フェロモンのみならず、他にも色々な目的のものがある。
集合フェロモン、警報フェロモン、攻撃フェロモン、足跡フェロモンなどなどである。
アリが行列を作ってゆくのは、歩きながら足跡フェロモンを道に着けてゆくためである。
ミツバチは針を一度刺すと、針の基部が引きちぎられて、ハチはやがて死ぬが、
酢酸イソアミルを主成分とする攻撃フェロモンが針と共に残り、
その香りに導かれて、周りのハチが一斉に襲い掛かる。
フェロモンには、性フェロモンのみならず、他にも色々な目的のものがある。
集合フェロモン、警報フェロモン、攻撃フェロモン、足跡フェロモンなどなどである。
アリが行列を作ってゆくのは、歩きながら足跡フェロモンを道に着けてゆくためである。
ミツバチは針を一度刺すと、針の基部が引きちぎられて、ハチはやがて死ぬが、
酢酸イソアミルを主成分とする攻撃フェロモンが針と共に残り、
その香りに導かれて、周りのハチが一斉に襲い掛かる。
フェロモンと云う言葉は、ギリシャ語の「フェライン」(運ぶ)と「ホルマン」(刺激する)の合成語である。
フェロモンは情報を運ぶ媒体である。
(2002年2月)
(参考文献) 桑原保正「性フェロモン」講談社叢書メチエ91、1996年