|
|
インダス文明における二進数 (二進数) |
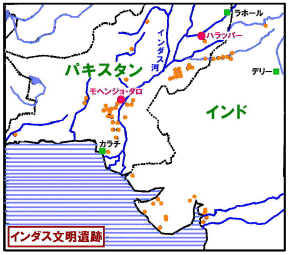
![]() インダス文明は紀元前二千年頃、インダス河の流域で栄えた文明である。
人類最古の四大文明(黄河流域、インダス河流域、チグリス・ユーフラテス河流域、ナイル河流域)
の一つと云われるものである。
インダス河上流のハラッパーと、下流のモヘンジョダロの二大都市を中心として三百にも及ぶ中小都市が発掘され、
整然とした碁盤目状の都市計画が発掘研究者の目を驚かせている。
インダス文明は紀元前二千年頃、インダス河の流域で栄えた文明である。
人類最古の四大文明(黄河流域、インダス河流域、チグリス・ユーフラテス河流域、ナイル河流域)
の一つと云われるものである。
インダス河上流のハラッパーと、下流のモヘンジョダロの二大都市を中心として三百にも及ぶ中小都市が発掘され、
整然とした碁盤目状の都市計画が発掘研究者の目を驚かせている。
ところで、このインダス文明においては、
数法として二進数が用いられていたのではないかと思わせる遺物が発見され、その驚きを倍加させられたと云う。
すなわち、モヘンジョダロの遺跡から出てきた分銅のセットがそのことを暗示していた。
その分銅のセットを軽い方から重い方へ並べて順番に秤量してゆくと、重さが2倍ずつになっているからである。
我々が通常用いている十進数であると、分銅の重さは10倍ずつになるはずである。
我が国のコインのように、間に5を差し挟むとすると、重さは5倍−2倍−5倍−2倍−となる。
我々にとっては、二進数はコンピューターの出現によって、ようやく知られるようになり、
ようやく用いられるようになったものである。
その二進数を四千年も前の人たちが日常的に用いていたと云うことは、卒倒する程の驚きである。
昔の人々を文明が未発達な時代の人たちと考えて無意識にでも軽蔑するのは、とんでもない誤りなのである。
考えてみると、我々が十進数を用いているのは、単に指が十本あるという所から来ただけのもので、
他には何の理由も、合理性も必然性もない。十進数よりも二進数の方が遙かに便利なのである。
重さを測る場合でも、一般的には、十進数より二進数の方が少ない分銅で測ることが出来るのである。