|
|
SCSI (Small Computer System Interface) |
"SCSI" は、 「スカジー」 と読みます。
コンピュータ用語の中でも、 読み方も意味も、 分かりにくいもののひとつです。
SCSI は、 パソコンに外付けのハードディスクや MO ドライブ、CD-R, CD-RW ドライブ
などの周辺装置を接続する方式 (インターフェイス) で、
これらの機器をパソコンに接続するには、 「SCSI ケーブル」 という専用ケーブルを使用します。
![]()
![]() ところが、 SCSI で接続される周辺装置では、 使用されているコネクタが必ずしも統一されていませんので、
SCSI ケーブルにはたくさんの種類があります。 左の写真はコネクタの一例です
(左端のものは
フルピッチ
ところが、 SCSI で接続される周辺装置では、 使用されているコネクタが必ずしも統一されていませんので、
SCSI ケーブルにはたくさんの種類があります。 左の写真はコネクタの一例です
(左端のものは
フルピッチ![]() の 50 ピンコネクタですが、
さすがに、 現在ではまず見かけません。
写真が小さいので分かりにくいかもしれませんが、 右の二つのコネクタも、 嵌合部の形状が全く違います)。
機器のコネクタに合ったケーブルを探すことから始めなくてはなりません。
の 50 ピンコネクタですが、
さすがに、 現在ではまず見かけません。
写真が小さいので分かりにくいかもしれませんが、 右の二つのコネクタも、 嵌合部の形状が全く違います)。
機器のコネクタに合ったケーブルを探すことから始めなくてはなりません。
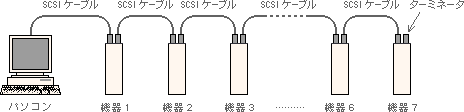
SCSI 機器には2個のコネクタがあって、 上図のように SCSI ケーブルで 7 台まで数珠つなぎにできます
(これを、ディジーチェーンといいます)。
いちばん端に接続された機器には 「ターミネータ」 というものを
接続![]() します。
します。
さらに、 このようにして接続された何台かの SCSI 機器を区別するために、 それぞれに重複しない ID 番号をつけます。
これには種々のタイプのスイッチが使われていますが、 下図右はその一例です。
 ターミネータ (上) |  ID 設定スイッチ |
このように、 SCSI インタフェースを使用して、 ハードディスクや MO ドライブ、 CD-R/RW ドライブ
などをパソコンに増設することができます。
SCSI は、 Small Computer System Interface の略で、
パソコンと周辺機器との間でデータを交換するために 1985年に作られたインターフェイスの規格です。
その後、 SCSI-2、SCSI-3 などの新たな規格も生まれました。
しかし、 SCSI には、 ターミネータだ、 ID だというわずらわしさがあります。
ディジーチェーンも簡単に見えますが、 例えば中間の機器を1個取り外すのは結構面倒です。
最近では周辺装置の種類を問わず、 もっと気軽に取り扱える USB などが普及し、
ハードディスクや MO ドライブ、 CD-R/RW ドライブなども USB で接続されるようになりました。
SCSI のお株は、 すっかり USB に奪われてしまったようです。