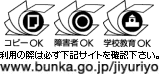|
|
補助記憶装置 (auxiliary storage) |
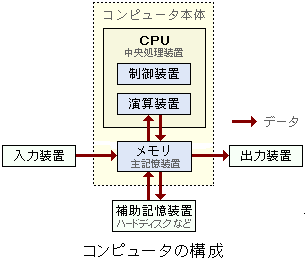
たとえばワープロでレポートを書いているとき、 そのワープロソフトのプログラムと書きかけのレポートのデータは、 メモリ (すなわち主記憶装置) が記憶しています。 キーを叩いて文章を入力するたびに、 データはメモリに蓄えられます。
レポートが完成、 あるいは今日はこれでお終いといって 「名前をつけて保存」 するときに使われるのが、 通常はハードディスク。 「いや私は USB メモリに」 という人がいるかもしれませんが、 どちらにしてもそれが補助記憶装置です
補助記憶装置はプログラムや文書データなどを、 「ファイル」 として保存しておくのに使われています。
一方メモリはコンピュータが動いている間中ずっと、 プログラムやデータを CPU とやりとりしながら忙しく働いています。
例えが適切ではないかも知れませんが、 補助記憶装置は毎月給料が 「どかん」 (あるいは 「どかん」 ) と振り込まれる銀行で、 まとまったお金の出し入れをしています。 銀行から引き出した当座のお金を入れておく財布は主記憶装置、 日々の買い物だの釣銭だのは、 財布とのやりとりです。
しかし、 補助記憶装置 (ハードディスク) が、 主記憶装置 (メモリ) 的に使われることもあります。
画像データなどを大量に読み込んでメモリの記憶容量が足りなくなると、 メモリに記憶されているデータのうち、 今は使われていない部分をハードディスクに戻してメモリを空け、 そこに必要なプログラムやデータを新たに読み込んで処理を続けます。 これを仮想記憶 (virtual memory)、 データを戻したりまた読み込んだりすることをスワップ (swapping) といいます。
ハードディスクが一時的にメモリの肩代わりをして、 メモリの容量が不足していてもコンピュータは動き続けます。 しかしハードディスクはメモリに比べるとうんと遅いため、 スワップが多発するとコンピュータの動きも鈍くなります。
また、 メモリ (DRAM) は揮発性ですから、 コンピュータをシャットダウンするとメモリが記憶していたプログラムもデータも全部消えてしまいます。 せっかく書いたワープロのデータや膨大なソフトウェアを保存しておくためには、 補助記憶装置が欠かせません。
主な補助記憶装置をまとめてみました。 ハードディスクや USB メモリの記憶容量は機種によって大幅に違いますが、 最近のパソコンには数百ギガバイト 〜 数テラバイト程度まで、 さまざまなものがつけられているようです。
| 名 称 | 記 録 方 式 | 記 憶 容 量 |
| ハードディスク | 磁気ディスク | さまざま(〜数TB) |
| USBメモリ/メモリカード | 半導体 | さまざま(〜数10GB) |
| ブルーレイ・ディスク | 光ディスク | 25GB |
| DVD-ROM/RAM | 光ディスク | 4.7GB |
| CD-ROM/R/RW | 光ディスク | 650MB |
| 関連事項: DRAM ハードディスク ハードディスク |