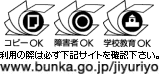|
|
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) |
ASCII は ANSI (American National Standards Institute; 米国規格協会) が 1963年に定めたキャラクタコードです。
「アスキー」 と読みます。
コンピュータが扱えるのは 2 進数の数値だけですから、 文書データをコンピュータで処理するには、 文字を数字に置き換えなくてはなりません。
ASCII では文字を 7 ビットの数字 (2 進数) で表わしています。
下図は ASCII コード表です。
8 列 × 16 行、 全部で 128 文字が入る表の中で、 たとえば "A" という文字は 0 から数えて 4 列目、 0 から数えて 1 行目にあります。 表のいちばん上と左にあるのは 16 進数 で表したこの列・行の数字で、 横方向には 0 から 7 までの 8 列、 縦方向には 0 から F まで 16 行あります。
"A" は 4 列目の 1 行目なので、 列・行の順に読んで 41 が "A" の文字コードです。 16 進数の 41 を 2 進数にすると 1000001、 10進数だと 65 です。 これが "A" につけられた背番号です。
文字が数字に置き換えられたので、 2 進数の数値だけしか扱えないコンピュータにも、 背番号を頼りに、 文字データを扱うことができるようになります。 ASCII を使うコンピュータはみな、 「65 番目の文字といえば "A"」 というわけで、 互いに文書データの交換や処理ができます。
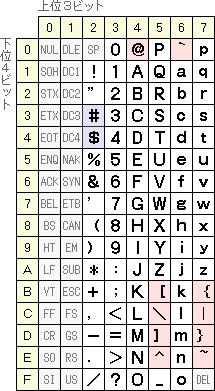
しかし ASCII は "American Standard Code for Information Interchange"、 つまり 「情報交換のためのアメリカ標準コード」 です。
英語にはよくても、 このままでは使えない国もあります。
そこで 1967年に国際規格化 (ISO 646
 " を選択し、
ピンクの部分は各国で自由に定めてよいことになりました。
" を選択し、
ピンクの部分は各国で自由に定めてよいことになりました。 イギリスやイタリアなどは 23 を "£" にし、 ドイツやフランスはピンクの部分に "
 "、 "
"、 " " などの文字を割り当てています。
日本は 5C の "\" (バックスラッシュ) を
"¥" (円記号) に、
7E の "~" (チルダ) を
" ̄" (オーバーライン) に置き換えて
JIS コード (JIS X 0201) としています。
" などの文字を割り当てています。
日本は 5C の "\" (バックスラッシュ) を
"¥" (円記号) に、
7E の "~" (チルダ) を
" ̄" (オーバーライン) に置き換えて
JIS コード (JIS X 0201) としています。00 〜 1F および 20 と 7F、 図では薄いグレーの部分に収められているのは文字ではなく、 制御文字 (control character) と呼ばれるものです。 例えば 08 の "BS" (Backspace) はキーボードの "BS" キーのコードで、 カーソルを戻して一文字削除する機能があります。 09 の "HT" (Horizontal Tabulation) は "TAB&" キーに対応していて、 カーソルの位置を一定の桁数だけジャンプさせます。 また 20 の "SP" は間隔 (スペース) です。
| 関連事項: | キャラクタコード (コンピュータの原理) キャラクタコード (用語解説) 2 進数 |