|
|
電卓戦争 |
1960 年代後半〜 1970 年代、 日本では電卓 (電子式卓上計算機) 産業が盛んになり、 最盛期には参入企業が 50 社以上に達しました。 各社入り乱れての開発競争 ・ 価格競争があまりにも熾烈であったため、 「電卓戦争」 と呼ばれたこともありました。
1. 黎明期の電卓
1964 年、 大井電気、 早川電機 (現シャープ)、 キヤノン各社から相次いで電卓が発売されました。
アレフゼロ101 はパラメトロン
しかしそのサイズは 40cm 前後、 重量は 20kg 程度と大きくて重く、 価格も 80〜40 万円 とたいへん高価でした。
大卒者の初任給が 21,500 円、 という時代です。
| 機種 | アレフゼロ 101
| コンペット CS-10A
| キャノーラ 130
|
|---|---|---|---|
| メーカー | 大井電気 | 早川電機 | キヤノン |
| 演算素子 | パラメトロン (1700個) | トランジスタ (530個) | トランジスタ (600個) |
| 寸法 | 55×52×38cm | 42×44×25cm | 35.5×46.7×22.5cm |
| 重量 | 17.5kg | 25kg | 15kg |
| 価格 | 80万円 | 53.5万円 | 39.5万円 |
2. 電卓のIC化
早川電機やキヤノンが発売したトランジスタ式電卓が好評を博すと、 それまではもっぱらリレー式計算器を作っていたカシオ計算機もトランジスタ式のカシオ 001 を開発し、 他のメーカーも続々と電卓市場に参入しました。
電卓を小型・低価格化するするためには、 部品点数を減らさなくてはなりません。 当初より電卓の小型化構想を持っていた早川電機は、 1966 年に世界で初めて IC を 28 個使った電卓、 CS-31A を発売しました。 しかしこれにはまだ 553 個のトランジスタが使われていました。
同じく早川電機は 1969 年、 米ロックウェル社の協力を得て、 電卓の機能を 4 個の LSI に集積した LSI 電卓 QT-8D を開発しました。
また、 1971 年にはビジコンが、 米モステック社と共同開発したワンチップ LSI を使った LE-120 を発売しました。
| 機種 | CS-31A
| QT-8D
| LE-120
|
|---|---|---|---|
| 発売年 | 1966年 | 1969年 | 1971年 |
| メーカー | 早川電機 | 早川電機 | ビジコン |
| 半導体 | IC (28個) +トランジスタ | MOS-LSI (4個) | MOS-LSI (1個) |
| 寸法 | 40×48×22cm | 13.5×24.7×7.2cm | 6.4×12.3×2.2cm |
| 重量 | 13kg | 1.4kg | 300g |
| 価格 | 35万円 | 9.98万円 | 8.98万円 |
IC 化 ・ LSI 化され、 部品点数が少なくなるにしたがって、
小型化、 軽量化、 低価格化が進んでいく様子が分かります。
こうして電卓の価格は 10万円を切るまでに下がりましたが、
当時大卒者の初任給が 46,400円 (1971年) ですから、
まだまだ個人が気軽に買えるという価格ではありませんでした。
3. マイクロプロセッサの誕生
世界初のワンチップ電卓 LE-120 を世に出したビジコンは、 1966年にもコアメモリを採用したメモリ付き電卓、
ビジコン161![]() を発売するなど、小さいながらもユニークな会社でした。
を発売するなど、小さいながらもユニークな会社でした。
ビジコンの社長小島義雄はまた、 仕様の異なった電卓をそのつど設計するのではなく、
電卓の機能は ROM に書き込んでおいて、 ROM のデータ、
すなわちプログラムを書き換えることによって様々な電卓を作ることができないかと考えました。
新しい電卓を作る度に新たにハードウェアを設計するのは、
人材に恵まれた大企業なら可能であっても、 ビジコンのような小企業では負担が大きいし、
製品価格も下げられないからです。
国内の半導体メーカーはこの電卓用 LSI の開発を引き受けてくれなかったので、
1970年にインテル (Intel) と協同開発および独占使用契約を結びました。
当時インテルは、 IC を発明したノイス (Robert Noyce) が、
半導体メモリを作るために 1969 年に作ったばかりの会社でした。
まだ経営が軌道に乗らず仕事も少なかったので、 日本の一小企業にすぎないビジコンと契約することになりました。
しかしインテルもビジコンも、 その時はまだ、 この LSI が大きな意味を持っていることに気づいていませんでした。
 i-4004 |  141-PF |
ビジコンのアイデアをもとに、 インテルのテッド・ホフ (Marcian E. "Ted" Hoff) が
4 ビットのマイクロプロセッサを考案、
ビジコンから派遣された嶋正利![]() が論理設計を行い、 ファジン (Federico Faggin) が回路の設計を担当して、
初のマイクロプロセッサ i-4004 が 1971年3月に誕生しました。
が論理設計を行い、 ファジン (Federico Faggin) が回路の設計を担当して、
初のマイクロプロセッサ i-4004 が 1971年3月に誕生しました。
10月には i-4004 を搭載したプリンタ付き電卓、
141-PF (159,800円) がビジコンから発売されました。
ビジコンとインテルの契約には両社が共同で LSI を開発すること、 開発費としてビジコンが 10 万ドル支払うこと、
製品はビジコンが独占販売権を持つこと、 製品出荷のスケジュールや価格などが取り決められていました。
しかし開発したマイクロプロセッサは電卓以外の用途にも広く使えることから、
インテルはビジコンと交渉して開発費の返却と製品の値下げを条件に、 ビジコンから i-4004 の外販許可を得ました。
一方ビジコンは、 電卓の熾烈な価格競争と、
オイルショックによる円高で輸出が激減したことなどによって、
1974 年に倒産![]() しました。
しました。
独占販売権の放棄がなければインテル同様、「世界のビジコン」 になっていた可能性もなくはありません。
ビジコンにとっては不運でした。
4. 電卓戦争の終焉
i-4004 を搭載した初めての電卓、 141-PF はプリンタ付きの高機能電卓でしたから価格も 159,800 円と高価でしたが、
この頃の標準的な電卓は 4 万円前後でした。
しかし当時の大学卒の初任給は 46,400 円です。
電卓はまだ業務用、 オフィスで計算をするためのものでした。
機種
カシオミニ
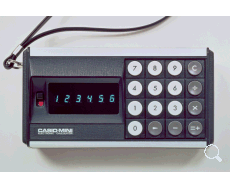
EL-805

LC-78
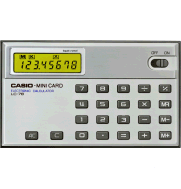
発売年 1972年 1973年 1978年
メーカー カシオ シャープ カシオ
特徴 低価格 初の液晶表示 名刺サイズ
寸法 146×77×42mm 78×118×20mm 91×55×3.9mm
重量 315g 200g 39g
価格 12,800円 26,800円 6,500円
電卓を一般の人々に、 算盤がわりに使ってもらいたいと考えたのはカシオでした。
そのために、 電卓の価格を 1 万円にしようという目標がたてられました。
1 万円電卓を実現するために、 機能も最小限に絞って開発されたのが 1 チップの 6 桁電卓 「カシオミニ」 でした。
個人が計算に使うのであれば、 6 桁でも 100万円まで計算できるから、 まあいいだろうというわけです。
発売価格は 12,800 円。
1 万円という目標は達成できませんでしたが、 それでもこれまでの 3 分の 1 の価格です。
カシオミニは大ヒットし、 他の電卓メーカーに大きな衝撃を与えました。
一方、 シャープは薄型電卓への道を探っていました。
当時の電卓には表示素子として蛍光表示管や LED が使われていました。
いずれも消費電力が大きいために単三電池が使われていて、 電卓の小型化、 特に薄型化の制約となっていました。
シャープが省電力化をはかるために注目したのは液晶でした。
液晶は材料の選択や配合が難しく、 寿命も短いため実用化は望めないと考えられていましたが、
電卓の表示装置として液晶ディスプレイの開発に成功し、 EL-805 が発売されました。
必ずしも低価格ではありませんでしたが、 単三乾電池一本で 100 時間も使える画期的な特徴によって、
これも大ヒットしました。
電卓の小型軽量化、 低価格化競争はますます激しくなり、 1978 年、
ついに名刺サイズで厚さ 3.9mm という LC-78 (カシオ) が現れました。
そして電卓が、 半導体技術、 生産技術、 低価格化、 小型軽量化、 省電力化など、
あらゆる面で行き着くところまで行ったときに、 気がつけばこれまで 50 社以上が参入していた電卓業界に、
残ったのはシャープとカシオだけでした。
熾烈を極めた電卓戦争はこうして終わりました。
米国ではもっぱら軍事・宇宙開発に使われた IC ですが、
日本では電卓という民生品に大量に使われて半導体産業を育て、
同時にマイクロプロセッサや液晶ディスプレイを生み出しました。
日本の電卓戦争は、 結果的に、 コンピュータの歴史に大きな影響を与えました。