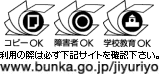|
|
キーボード (keyboard) |

最近はすっかり姿を消して、 映画か博物館でしか見ることができませんが、 学生時代には私も使いました。 活字の一部を入れ替えてドイツ語の "
 " やウムラウトが打てるように改造してもらい、
さあ勉強しようと決心、 したこともあります。
" やウムラウトが打てるように改造してもらい、
さあ勉強しようと決心、 したこともあります。キーを押すと活字がついたバーが立ちあがって、 インクリボン越しに用紙をパカンと叩いて文字を印刷します。 左の写真(下) は少し見にくいですが、 その様子です (クリックすると拡大されます)。 上手なタイピストが打つと何本もの活字のバーが入り乱れて踊りますが、 速く打ちすぎると絡まってしまいます。
キーから指を離すと活字が戻り、 同時にキャリッジごと用紙が一文字分左に動きます。 一行打ち終わると写真(上) の左上に少し見えているレバーでキャリッジを右端まで戻し、 用紙を一行分上げます。 この操作を 「キャリッジ・リターン」 と 「ライン・フィード」 といいますが、 コンピュータも同じことをするのに "CR" (0D) と "LF" (0A) というコード を使っています

コンピュータのキーボードにはその制約がなく、 整然と碁盤の目状に配置できますが、 タイプライターに慣れた人には打ちにくいのでしょうか、 こんなところまでそっくりです。
もうひとつそっくりなのはキー配列です。
一般的に使われているキーボードは英字上段に左から "Q・W・E・R・T・Y・…" と並んでいることから、 「QWERTY (クワーティ) 配列」 といいます。
アルファベット順ではないので慣れるまで大変で、 タイプライターを打ちやすくするために考え出されたんだろうと思いがちですが、 実はそうではありません。
下表は 「ロミオとジュリエット」 で使われている文字数を数えたものです (四捨五入しているため、 合計は 100 %になりません)
この表で分かるように、 英文でよく使われる文字は E、T、O、A、I、H、S などですが、 QWERTY 配列のキーボードではこれらはいずれも上段にあるか、 左手や、小指、薬指に割り当てられていて、 打ちやすい文字は H だけです。
上にも書きましたが、 タイプライターを速く打ちすぎると活字のバーが絡まってしまうので、 絡まりにくいように工夫されたと言われています。
| 文字 | 文字数 | % | 文字 | 文字数 | % | 文字 | 文字数 | % |
| A | 8,240 | 7.79 | J | 277 | 0.26 | S | 6,584 | 6.22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1,715 | 1.62 | K | 831 | 0.79 | T | 9,709 | 9.17 |
| C | 2,284 | 2.16 | L | 4,976 | 4.70 | U | 3,759 | 3.55 |
| D | 3,934 | 3.72 | M | 3,358 | 3.17 | V | 1,109 | 1.05 |
| E | 12,818 | 12.12 | N | 6,468 | 6.11 | W | 2,519 | 2.38 |
| F | 2,030 | 1.92 | O | 8,805 | 8.32 | X | 125 | 0.12 |
| G | 1,838 | 1.74 | P | 1,551 | 1.47 | Y | 2,623 | 2.48 |
| H | 6,787 | 6.41 | Q | 65 | 0.06 | Z | 32 | 0.03 |
| I | 6,909 | 6.53 | R | 6,488 | 6.13 | 記号 | 6,646 | --- |
下図は 「ロミオとジュリエット」 の冒頭部ですが、 これを QWERTY 配列のキーボードで入力したとき、 指を上下に動かさなくてはならない文字に色をつけてあります。 ピンクの文字は上段、 ブルーの文字は下段にあります。
ロミオとジュリエット全文を入力した場合、 QWERTY 配列のキーボードだとホームポジションで打てる文字は 34% しかありません。
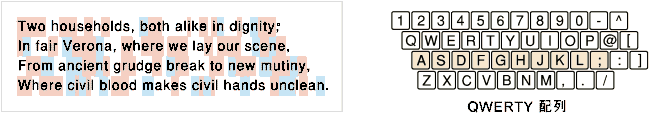
下図は、 あまり見かけませんが DVORAK (ドボラック) 配列といいます。
よく使われる文字がホームポジション
DVORAK 配列だと 66% がホームポジションで打てます。
どちらが打ちやすいかは言うまでもありません。
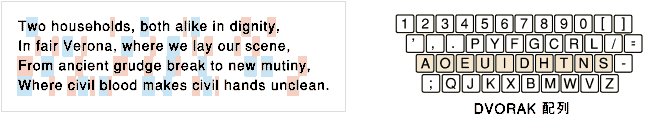
タイプライターには不合理な配列もやむを得なかったかもしれませんが、 コンピュータの入力装置に使われるようになったときにも、 キー配列は見直されませんでした。
おそらく当時、 コンピュータのデータ入力に動員されたのはタイピストでしょう。
おっかなそうなコンピュータの前に連れてこられて、タッチが違うキーボードで、 その上配列が馴染みの QWERTY でなかったら、 ストライキを起こしたに違いありません。
かくしてデファクトスタンダード (de facto standard)
コンピュータ技術者たちも、 まさか 50 年後、 何十億もの人々がコンピュータを使うようになるとは、 夢にも思わなかったのでしょう。
もしそれが予測できていたら、 使いやすいキーボードの研究を最優先したでしょうに…。