|
|
テルモピレの戦い(情報伝達) |
紀元前480年、ペルシャは再びギリシャへの遠征をはかる。第三次ペルシャ戦争である。
ダリウス1世の後を継いだクラルクセス1世(在位 BC486〜465)は、
自ら十万の陸軍と一千隻の海軍を率いてギリシャに襲いかかる。
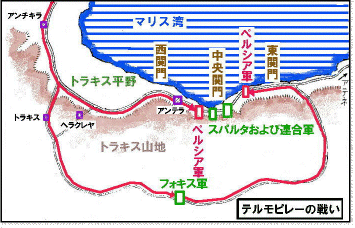 エーゲ海の北岸を迂回してテッサリアから南下してくるペルシャの陸軍を、
ギリシャはテルモピレ (Thermopylai) の隘路を防衛線として防ごうとする。
テルモピレは 「熱い門」 の意味であり、カリドロモス山の峻険な岩山がそそり立って
マリス湾に落ちる断崖に通じた狭い道である。
数列の縦隊しか進めない。
この天険の地を守るのは、スパルタの王レオニダス自らが率いる僅か七千の兵。
そして、三日間にわたる凄惨な死闘が展開される。
しかし、ある裏切り者がペルシャ軍に間道を教える。
このため、二日目の夕刻から、カリドロモス山中の間道を夜を徹して分け入ったペルシャの 「不滅隊」(カタナイト)
に背後を突かれる。
レオニダス王以下三百のスパルタ精兵と、七百のテスピアイの兵士たちは、
ペルシャ軍の投降勧告にも応ぜず、最後まで踏みとどまり、一兵となるまで戦い、遂に全員が玉砕してしまう。
エーゲ海の北岸を迂回してテッサリアから南下してくるペルシャの陸軍を、
ギリシャはテルモピレ (Thermopylai) の隘路を防衛線として防ごうとする。
テルモピレは 「熱い門」 の意味であり、カリドロモス山の峻険な岩山がそそり立って
マリス湾に落ちる断崖に通じた狭い道である。
数列の縦隊しか進めない。
この天険の地を守るのは、スパルタの王レオニダス自らが率いる僅か七千の兵。
そして、三日間にわたる凄惨な死闘が展開される。
しかし、ある裏切り者がペルシャ軍に間道を教える。
このため、二日目の夕刻から、カリドロモス山中の間道を夜を徹して分け入ったペルシャの 「不滅隊」(カタナイト)
に背後を突かれる。
レオニダス王以下三百のスパルタ精兵と、七百のテスピアイの兵士たちは、
ペルシャ軍の投降勧告にも応ぜず、最後まで踏みとどまり、一兵となるまで戦い、遂に全員が玉砕してしまう。
その壮絶な戦いは、ギリシャの人々の心を激しく揺り動かした。そして、詩人シモニデスは歌った。
「見知らぬ旅人よ、行きてラケダイモン(スパルタ)の人に伝えよ。われら命に服して、ここに眠ると」
この詩を刻んだ石碑は、今もテルモピレの古戦場に建っていると云う。
それは、現代でも人の心を打つ戦史であり、私もまた深い感動を受けるが、それにも増して、私は、
「見知らぬ旅人よ」という詩人の言葉に心が捕らえられる。
当時は、情報を伝達し媒介するのは、ただ一つ人間そのものだけであった。
もとより、電話も電信もない。ラジオもない。テレビもない。
彼らの壮絶な最後を故郷の人たちに伝えてくれるのは、旅人しかいない。
たまたまここを通って、折り重なった屍を見た旅の商人、
それだけが、自分たちの最後を故郷の親や子に知らせてくれるかも知れないものなのである。
何と頼りないことか。何と心もとないことか。
もし、誰も通りかからねば、わが屍は徒に草蒸して朽ちるだけである。
私はその「見知らぬ旅人よ」という言葉に、何ともやるせないものを感じてしまう。
情報伝達が人の移動のみでしか行われなかつた時代、すなわち、「通信=交通」という時代というものを、
つくづくと思うのである。
(参考文献) 村田数之亮「ギリシャ」(世界の歴史4)河出書房、1968年、