|
|
米相場の旗振り通信 (通信) |
明治時代になっても、電気通信の普及は遅々たるものであった。
米相場師たちにとっては、大阪堂島の米市場の相場の上がり下がりを、 いち早く知ることが、成功不成功の鍵であった。
そこで、大和の相場師源助が旗振り通信と云うものを考えた。
この方法は、あっと云う間に相場師たちの間に広まった。
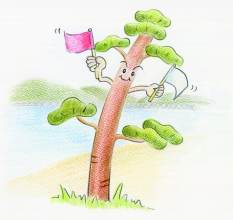
![]() 吹田市の高浜神社の境内の松林の中に、一きわ高く聳えて、遠く淀川の長柄堤からも見ることができる松があった。
この松は、後嵯峨天皇が訪れて詠んだ
「来て見れば千代も経ぬべし高浜の松に群れいる鶴の毛ごろも」
の歌にちなんで、「鶴の松」 と呼ばれていたが、 この松もまた、旗振り通信の中継点として用いられたので、
「旗振り松」とも呼ばれていた。
しかし、ここで、どのような方法で旗が振られていたのかは、よく分からない。
吹田市の高浜神社の境内の松林の中に、一きわ高く聳えて、遠く淀川の長柄堤からも見ることができる松があった。
この松は、後嵯峨天皇が訪れて詠んだ
「来て見れば千代も経ぬべし高浜の松に群れいる鶴の毛ごろも」
の歌にちなんで、「鶴の松」 と呼ばれていたが、 この松もまた、旗振り通信の中継点として用いられたので、
「旗振り松」とも呼ばれていた。
しかし、ここで、どのような方法で旗が振られていたのかは、よく分からない。
交野市の東に連なる山並みの最高峰たる旗振山 (標高356m) も、その名が示すように、 旗振り通信の中継点であった。
ここでは、白旗と黒旗で信号を送ったと云われているが、これも詳細は分からない。
神戸の須磨浦の北の山にも旗振山 (標高253m) がある。
ここでは、麓の部落に住んでいる旗振人が、 弁当を持って毎日登ってきて、
東にある高取山の中継点で振られる旗を、 望遠鏡で懸命に見ながら旗を振ったと云われており、
旗は白旗で、快晴の日は畳半分ほどの小旗、曇天の日は畳一枚ほどの大旗を振ったと云う。
このように、調べてみると、当然のことながら、旗振り通信の中継点だったと今も伝えられている場所は数多い。
旗振山とか旗振り場などの名が、あちこちに残っており、さらには、旗振台古墳と云う名の所 (岡山市の東部) まである。
とは云え、旗振りの中継点であったことを示すものが何か残っている訳ではない。
 石堂ケ岡の米相場の碑 |
(改訂: 2003年3月)