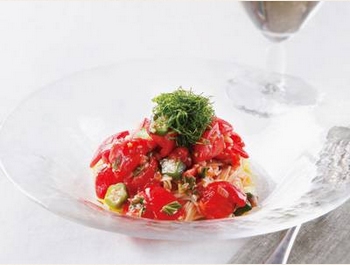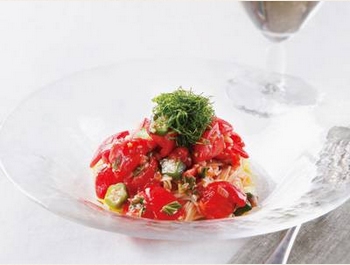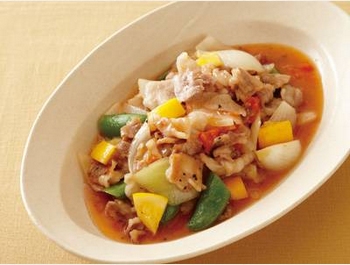ゆっくりと冷蔵庫でつけていくぬか漬けは、米麹が入っていて風味抜群。塩分を控えたヘルシーレシピで紹介します。

| 講師: 奥村 彪生 |
(つくりやすい分量) | |
| ・生ぬか | 1.5kg |
| ・粗塩 | 150g |
| ・水 | 1.2リットル |
| ・米麹 | 150g |
| ・湯 | カップ3/4 |
| ・削り節 | 3袋(12g) |
| ・にんにく | 10g |
| ・赤とうがらし | 3本 |
| ・昆布 | 20g |
| ・捨て漬け用野菜 | 150〜200g(1回分) |
ぬか床をつくる -米麹をふやかし、塩水とぬかを混ぜる- | ||||||||||||||||||||||||||
 | 米麹は分量の湯を注いで約30分間おき、ふやかしておく。ボウルに分量の水を入れて粗塩を加え、よく混ぜて溶かす。 | |||||||||||||||||||||||||
 | 別の大きなボウルに生ぬかを入れ、 | |||||||||||||||||||||||||
 | ボウルの底から両手ですくい上げるようにして混ぜ、ぬかの粉っぽさがなくなるまでまんべんなく塩水を含ませる。 | |||||||||||||||||||||||||
ぬか床をつくる -香りやうまみの材料を混ぜる- | ||||||||||||||||||||||||||
 | | |||||||||||||||||||||||||
 | ふやかした米麹を加える。 | |||||||||||||||||||||||||
 | 両手でボウルの底からよく混ぜる。 | |||||||||||||||||||||||||
ぬか床をつくる -捨て漬けをする- | ||||||||||||||||||||||||||
 | 漬物容器の底に | |||||||||||||||||||||||||
 | 表面を押して平らにならす。 | |||||||||||||||||||||||||
 | 容器の内側や縁についたぬかをきつく絞ったぬれ布巾できれいに拭き取る。容器のふたをして、冷蔵庫へ入れる。 | |||||||||||||||||||||||||
ぬか床をつくる -捨て漬けを繰り返して完成- | ||||||||||||||||||||||||||
 | 2〜3日後、捨て漬け用野菜を取り出し、野菜についたぬかをしごいて戻す。よく混ぜ、新たに捨て漬け用野菜150〜200gを | |||||||||||||||||||||||||
野菜を漬ける | ||||||||||||||||||||||||||
 | 野菜は漬かりやすい形に切るなどの下ごしらえをして、ぬか床に入れる。きゅうりの場合は洗って水けを拭き、しま目に皮をむく。1本につき粗塩小さじ1/3をもみ込む。 | |||||||||||||||||||||||||
 | なすは、粗塩とみょうばんを2:1の割合で混ぜて、1本につき小さじ1/3をほんのり紫色が出るまでもみ込む。ヘタをつけたまま縦に深く切り目を入れる。みょうばんを使うと、色が鮮やかになる。 | |||||||||||||||||||||||||
 | ぬか床に完全に埋め込み、表面を平らにならす。容器の内側をきつく絞ったぬれ布巾できれいに拭き、ふたをして冷蔵庫に入れる。減塩ぬか床のため、漬かるまで少し時間がかかる。きゅうり、なすともに1〜2日間で程よく漬かる。 | |||||||||||||||||||||||||
 | 野菜についたぬかをしごいて床に戻し、取り出す。水で洗い、食べやすい大きさに切る。 | |||||||||||||||||||||||||
ぬか床の手入れ -毎日すること- | ||||||||||||||||||||||||||
 | 毎日、最低1回は底からしっかり混ぜるのが基本。空気を入れることで、乳酸菌や酵母などが活性化してバランスが整い、腐敗を防げる。混ぜたら、ぬかの表面を平らにならし、容器の内側をきつく絞ったぬれ布巾できれいに拭き、ふたをして冷蔵庫に入れる。 | |||||||||||||||||||||||||
ぬか床の手入れ -時々すること- | ||||||||||||||||||||||||||
 | 野菜の水分が出てぬか床がゆるくなったら、乾いた布巾をのせて水分を吸い取る。状態を見て、生ぬか二つかみから三つかみとその1/6量の粗塩を補ってよく混ぜる。昆布や削り節を足すと風味もよくなる。 | |||||||||||||||||||||||||
 | 発酵が進みすぎて酸っぱくなったときは、重曹大さじ1を加えて混ぜる。こうすると、酸が中和されて酸味がやわらぐ。 | |||||||||||||||||||||||||
ぬか床の手入れ -しばらく休ませたいとき- | ||||||||||||||||||||||||||
 | 1週間くらいなら、粗塩大さじ6を混ぜ、ふたをして冷蔵庫で保存。長期間の場合は表面をならし、1cm厚さの粗塩で覆う。再開するときは、上の粗塩を除き、生ぬかカップ1を足して混ぜる。 | |||||||||||||||||||||||||
| 《捨て漬け用野菜》
| キャベツの外葉、大根の葉や皮などのくず野菜。洗って、水けをきったもの。
| 《漬物容器》
| 深さ約10cm、容量約4.3リットルのふた付きの密封容器を使用。プラスチック製が軽くて扱いやすい。きれいに洗って乾かしておく。
| 《香りやうまみの素(もと)となる材料》
| 米麹(甘みを添え、乳酸発酵を促す)、削り節(うまみと香ばしさをプラス)、にんにく(雑菌を防ぎ、野菜の香りを生かす)、赤とうがらし(防虫効果、減塩をカバー)、昆布(うまみを出す)。
| | ||||||||||||||||||||