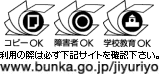|
|
ピクセル (画素) |
ディスプレイ装置の画面に表示する色情報の最小単位を 「画素」 (ピクセル: pixel
下図左は 32×24 ピクセルで構成されている画像で、 右はこれを 8 倍に拡大してあります。
拡大画像の小さい正方形が元の画像の 「画素」 で、 画素ごとにそれぞれの色を表示しています。
コンピュータのディスプレイは、 メモリに記憶されている各画素の色のデータを表示しています。
上図のようなフルカラー表示では、 赤・青・緑の各色を 8 ビット (256 階調) で表わしていますから、 1 画素当たり 3 バイト、 32×24 画素の画像なら 32×24×3 = 2,304 バイトのメモリの情報を表示しています。 ディスプレイ全体では、 たとえば 1,280×960 ピクセルのディスプレイなら 1,280×960×3 = 3,686,400、 約 3.5M バイトになります。
一方、 モノクロディスプレイの場合は 1 画素あたり 1 ビットでいいので、 1,280×960÷8 = 153,600、 153k バイトですみます。
ディスプレイの画素構成には、 主なものだけでも次のように、 多くの種類があります。
| QVGA | Quarter VGA: | 320×240 pixel |
|---|---|---|
| VGA | Video Graphics Array: | 640×480 pixel |
| SVGA | Super VGA: | 800×600 pixel |
| XGA | eXtended Graphics Array: | 1024×768 pixel |
| SXVGA | Super eXtended VGA: | 1280×960 pixel |
| UXGA | Ultra XGA: | 1600×1200 pixel |
VGA (Video Graphics Array) はかつての IBM PC に採用されてパソコン用ディスプレイの標準として普及したもので、 以後高解像度のディスプレイでも 「スーパー VGA」 など、 VGA を基準にした呼び方がされています。 多くは画面の縦横比も VGA と同じ 4:3 です。
比較しやすいように、 画素は皆同じ大きさとして各サイズのディスプレイを図にすると、 次のようになります。
上段左端が VGA、 現在は SXVGA かそれ以上、 また横長のディスプレイも増えて、 HDTV (高精細テレビ) と同じ横 16:縦 9 に合わせた 1920×1080 pixel なども使われています。
下段は携帯電話やタブレット端末などのディスプレイです。
数年前の携帯電話は QVGA、 画素数では VGA の 1/4 のサイズが中心でしたが、 これも次第に高精細化され、 スマートフォンでは画素数で QVGA の 5〜8 倍のものが使われています。